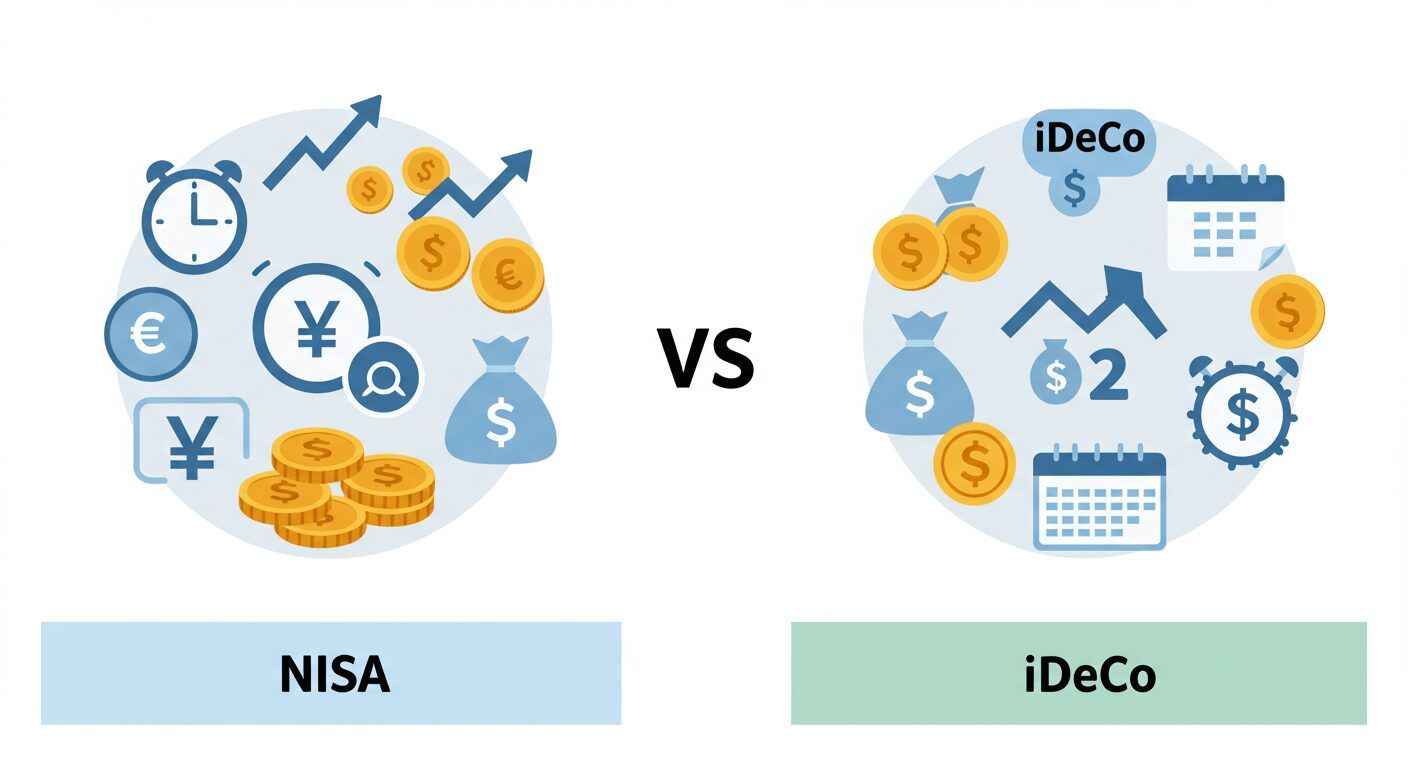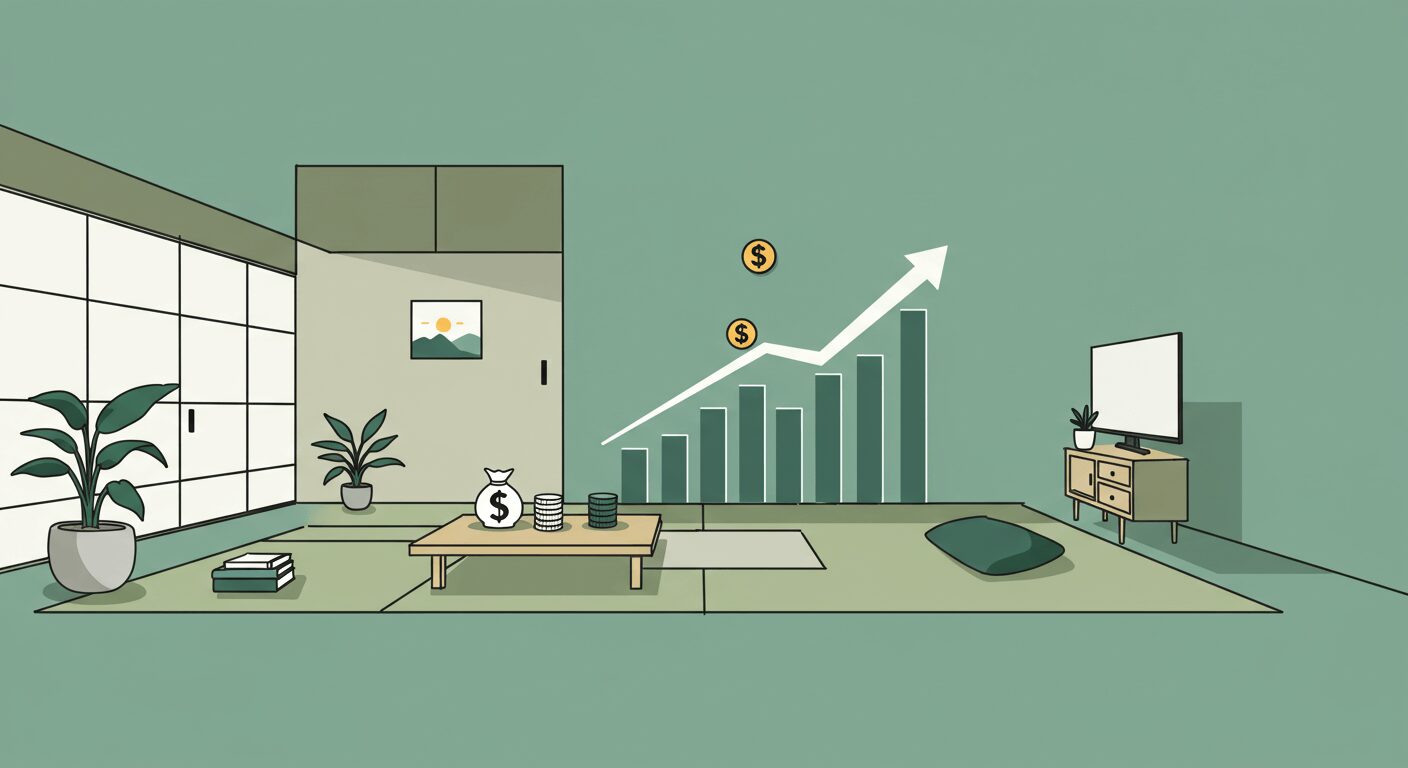【投資初心者向け】リスクを抑えて資産を増やす方法を解説!

かつての日本では、銀行預金に高い金利がついていたため、単に預けておくだけでも資産が増えていく時代がありました。
しかし、現在は預金金利が極めて低い水準にあり、その効果はほとんど期待できません。
さらに、インフレが進むと、同じ金額で買えるモノやサービスの量が減り、現金の価値は実質的に目減りしてしまいます。
このような時代だからこそ、「投資」による資産形成が重要になっています。
とはいえ、「投資は難しそう」「損をするのが怖い」という不安から、踏み出せない方も多いのではないでしょうか。
そのためこの記事では、投資未経験の初心者の方向けに、投資の基本知識から始め方、リスクを抑えながら資産を増やすためのポイントまで、分かりやすく解説します。
金融庁や日本証券業協会などの信頼できる情報源を基に、安心して投資を始めるための道しるべとなる情報をお届けします。
投資の基本を理解しよう
投資を始める前に、基本的な概念や種類、リスクとリターンの関係について理解しておくことが大切です。
ここでは投資の定義から各種類の特徴、そしてリスク管理の基本までを解説します。
投資とは何か?
「投資」とは、将来的な利益を見込んで、現在のお金(資金)を株式や投資信託などの金融商品に投じる行為です。
その主な目的は、将来に向けて資産を増やすことにあります。
一方、「貯蓄」は、一般的にお金を銀行などに預けることを指します。
反対に投資は、貯蓄とは異なり元本保証がありません。
投資の最も基本的な目的は「資産を増やすこと」ですが、それ以外にも重要な目的があります。
- インフレ対策
物価が上昇するインフレ局面では、現金の価値は実質的に目減りします。投資は、インフレに強いとされる資産(株式や不動産など)に資金を振り向けることで、資産価値の目減りを防ぎ、維持・向上させる役割を持ちます。 - ライフプランの実現
老後の生活資金、子どもの教育資金、住宅購入資金など、人生の様々な目標(ライフプラン)を実現するために必要となる資金を準備する手段としても、投資は活用されます。
投資を始める際には、まず「なぜ投資をするのか」「いつまでに、いくら必要なのか」といった自身の目的を明確にすることが重要です。
目的によって、取るべきリスクの度合いや適切な投資期間、選ぶべき金融商品などが変わってくるためです。
投資の種類
投資対象となる金融商品には様々な種類がありますが、代表的なものとして「株式」「債券」「投資信託」「不動産」があります。
それぞれの特徴、リスク、リターンを理解しておきましょう。
「株式(Stocks)」は、企業が事業活動に必要な資金を集めるために発行する証券です。
株式を購入することは、その企業の一部を所有すること(株主になること)を意味します。
株主は、企業の成長に伴う株価の値上がりによる利益(キャピタルゲイン)や、企業が得た利益の一部を還元する配当金(インカムゲイン)などの恩恵を受けることが期待できます。
「債券(Bonds)」は、国や地方公共団体、企業などが、投資家から資金を借り入れるために発行する「借用証書」のようなものです。
発行時に、満期日(償還日)と、それまでに支払われる利子の利率があらかじめ決められています。
投資家は、定期的に利子を受け取り、満期日には額面金額(元本)が返還されます。
「投資信託(Investment Trusts / Funds)」は、多くの投資家から集めた資金を一つにまとめ、運用の専門家(ファンドマネージャー)が株式や債券、不動産など国内外の様々な資産に分散して投資・運用する金融商品です。
運用によって得られた利益は、投資額に応じて投資家に分配されます。
「不動産(Real Estate)」は、マンション、アパート、オフィスビルなどの不動産を購入し、それを賃貸に出して家賃収入(インカムゲイン)を得たり、購入時よりも高く売却して売却益(キャピタルゲイン)を得たりする投資方法です。
これらの投資対象を比較したとき、初心者の方には特に「投資信託」がおすすめです。
その理由は、「少額から始められる点」、「専門家による運用が受けられる点」、そして「分散投資効果によりリスクを抑えられる点」にあります。
投資のリスクとリターン
投資には必ずリスクが伴います。「リスクを0にして利益だけを得る」という投資は存在しません。
しかし、リスクを理解し、適切に管理することで、より安定した資産形成を目指すことは可能です。
投資の世界で使われる「リスク」という言葉は、日常会話で使われる「危険」という意味合いとは少し異なります。
投資におけるリスクとは、主に「リターン(収益)の不確実性」や「価格(価値)の変動の可能性(振れ幅)」を指します。
一般的に、期待されるリターンが高いほど、リスクも高くなる傾向があります(ハイリスク・ハイリターン、ローリスク・ローリターン)。この関係性を理解しておくことが重要です。
また、投資には様々なリスクが伴いますが、主なものとして以下のリスクを理解しておきましょう。
- 価格変動リスク
投資した金融商品の価格が、景気や経済の状況、企業の業績、市場の需給バランスなど様々な要因によって変動するリスクです。 - 信用リスク
株式の発行企業や債券の発行体が、経営不振や財政難、倒産などに陥り、当初予定されていた利息や元本の支払いが滞ったり、株式の価値が大幅に下落したりするリスクです。 - 流動性リスク
保有している金融商品を、売りたい時に希望する価格で、または希望する量だけ売却できない可能性があるリスクです。 - 為替変動リスク
外国の株式、債券、投資信託、外貨預金など、外貨建ての資産に投資する場合に発生するリスクです。
これらのリスクに対処するための基本的な考え方が、「長期・積立・分散」という3つの原則です。
これらを組み合わせることで、リスクを効果的に管理し、より安定した資産形成を目指すことができます。
長期投資は、数年~数十年といった長い期間にわたって資産を保有し続ける投資スタイルです。
短期的な価格の上下に一喜一憂せず、投資対象の長期的な成長や価値の上昇に期待します。
投資期間が長くなるほど、一時的な市場の好不調が平均化され、年あたりのリターンが安定する傾向があります。
積立投資(ドル・コスト平均法)は、毎月1万円、毎週5000円など、「定期的」に「一定の金額」で同じ金融商品を継続して購入していく投資手法です。
毎回一定額を購入するため、価格が高い時には購入できる口数(量)が少なくなり、価格が安い時には多くの口数を購入することになります。
これにより、結果的に平均購入単価を引き下げる効果が期待でき、高値掴みのリスクを軽減できます。
分散投資は、「卵は一つのカゴに盛るな」という投資格言が示す通り、投資対象を一つに集中させず、複数の異なる対象に分けて投資することで、リスクを軽減する手法です。
特定の投資対象が値下がりしても、他の投資対象の値上がりでカバーし、資産全体の値動きを安定させる効果が期待できます。
分散には、「資産(種類)の分散」、「地域(国)の分散」、「時間(タイミング)」の分散という3つの観点があります。
初心者におすすめの投資方法
投資の基本を理解したところで、次はどのように投資を始めれば良いのか。
ここでは、特に初心者にとって取り組みやすい投資信託の活用法から、リスクを軽減する積立投資、さらに税制優遇を受けられるNISA・iDeCoの活用法まで、具体的に解説します。
少額から始めて、長期的に資産を育てていくための手法を身につけましょう。
少額から始められる投資信託
先ほどもお伝えしたように、投資信託は初心者に特におすすめの金融商品です。
そして、投資信託を選ぶ際のポイントは以下の通りです。
何のために投資するのか、いつまでにいくら必要か、そしてどの程度の価格変動なら許容できるかを考えることが大切です。老後資金のような長期的な目標であれば多少リスクを取ることも可能ですが、数年内に使う予定の資金であれば安定性重視となります。
その投資信託が、主に何に投資しているかを確認しましょう。資産クラス(株式、債券など)、地域(日本、米国、全世界など)、分散の度合いなどをチェックします。初心者には、より多くの資産や地域に分散されているファンドがおすすめです。
- インデックスファンド
日経平均株価や米国のS&P500指数といった、特定の市場指数(ベンチマーク)と同じような値動きを目指す運用方針のファンドです。市場全体の平均的なリターンを目指すため、値動きが比較的わかりやすく、運用にかかるコスト(信託報酬)が低い傾向にあります。初心者にはこちらがおすすめです。 - アクティブファンド
市場指数を上回るリターンを目指し、ファンドマネージャーが独自の調査や分析に基づいて投資する銘柄やタイミングを判断するファンドです。市場平均以上のリターンが期待できる可能性がある一方、運用がうまくいかなければ市場平均を下回るリスクもあり、コストも高めです。
投資信託には購入時手数料、信託報酬(運用管理費用)、信託財産留保額などのコストがかかります。長期運用の場合、わずかなコスト差でも最終的なリターンに大きな影響を与えるため、できるだけ低コストのファンドを選ぶことが重要です。
過去の基準価額の推移や年間収益率、そしてファンドの規模を示す純資産総額をチェックしましょう。純資産総額が安定して増加しているファンドは、多くの投資家から支持されていると考えられます。一般的に、数十億円以上が一つの目安とされます。
初心者には、全世界や米国などの広範な市場指数に連動する、低コストのインデックスファンドが推奨されることが多いです。
例えば、以下のようなファンドが人気です。
- eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)
日本を含む先進国および新興国の株式市場全体に連動することを目指すファンド。これ1本で世界中の株式に幅広く分散投資できる手軽さが人気です。 - eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
米国の代表的な株価指数であるS&P500指数に連動することを目指すファンド。近年の米国株式市場の好調さから人気を集めています。 - SBI・V・S&P500インデックス・ファンド
上記と同様にS&P500指数への連動を目指すファンドで、特に信託報酬の低さが特徴です。
これらのファンドは、多くの場合、後述するNISA(つみたて投資枠・成長投資枠)の対象にもなっているため、税制優遇と組み合わせて活用するのも効果的です。
積立投資でリスクを軽減
積立投資(ドル・コスト平均法)は、投資初心者にとって最も取り組みやすく、かつリスクを抑える効果が期待できる投資手法です。
毎月一定額を決まった商品に投資し続けるこの方法には、心理的な負担を軽減する効果もあります。
市場価格が高い時には少ない口数しか買えませんが、安い時には多くの口数を購入できるため、結果として平均取得単価は市場の平均価格よりも低くなる傾向があります。
それから、積立投資(ドル・コスト平均法)のメリットは、以下のようにまとめられます。
- 購入タイミングに悩む必要がない
相場の予測は専門家でも難しいものです。定期的に一定額を投資することで、「今が買い時か」「もう少し待った方がいいか」といった判断のストレスから解放されます。 - 少額から始められ、計画的に投資を続けやすい
月々5,000円や10,000円など、自分の予算に合わせた金額から始められるため、負担が少なく継続しやすいのが特徴です。 - 感情に左右されずに投資を継続しやすい
相場が下落した時に怖くなって売却してしまったり、逆に相場が上昇した時に調子に乗って大きく買い増したりといった、感情的な判断による失敗を防ぎやすくなります。
ただし、積立投資(ドル・コスト平均法)は、購入単価を平準化する効果はありますが、投資収益を保証するものではありません。
価格が下落し続けるような局面では、損失を被る可能性もある点には注意が必要です。
積立投資を始める際は、自分の収入や生活費を考慮して、無理なく続けられる金額を設定することが大切です。
月々5,000円や10,000円といった少額からでも、長期間継続することで大きな資産形成につながる可能性があります。これこそが「長期・積立・分散」投資の真髄と言えるでしょう。
NISA・iDeCoを活用しよう
投資を始める際に、ぜひ活用したいのが税制優遇制度である「NISA(ニーサ)」と「iDeCo(イデコ)」です。
これらの制度を利用することで、通常、投資で得た利益(運用益)にかかる約20%の税金が非課税になるなどのメリットがあります。
「NISA(新NISA)」は、個人のための税制優遇制度として2014年に始まり、2024年からは制度が大幅に拡充され、恒久化されました。
新NISAでは、「つみたて投資枠」と「成長投資枠」という2つの枠を併用できます。
年間投資上限額は120万円。金融庁が定めた、長期の積立・分散投資に適しているとされる一定の投資信託およびETF(上場投資信託)に限定されています。定期的に一定額を買い付ける「積立投資」のみ可能です。
年間投資上限額は240万円。上場株式、投資信託、ETF、REIT(不動産投資信託)など、つみたて投資枠よりも幅広い商品が対象です。一度にまとまった金額で購入する「一括投資」と、「積立投資」の両方が可能です。
新NISAの大きなメリットは、NISA口座内での投資から得られる譲渡益(売却益)や配当金・分配金には、期間の制限なく税金がかからない点です。
通常約20%課税される分も再投資に回せるため、複利効果を高め、効率的な資産形成が期待できます。
「iDeCo(個人型確定拠出年金)」は、公的年金(国民年金・厚生年金)に上乗せする形で、自分で掛金を拠出し、自分で選んだ金融商品で運用することで、老後のための資産を形成する私的年金制度です。
iDeCoの最大のメリットは、税制優遇措置が非常に手厚い点です。
※ただし、iDeCoは原則として60歳まで引き出すことができない点が大きな特徴です。
老後資金準備のための制度であるため、途中で急にお金が必要になった場合でも、簡単には引き出せません。
また、NISAとiDeCoの主な違いを表にまとめると、以下のようになります。
NISAとiDeCoの比較表(タップして表を開く)
| 項目 | NISA(つみたて投資枠) | NISA(成長投資枠) | iDeCo |
|---|---|---|---|
| 目的 | 自由(長期・積立・分散投資向け) | 自由 | 老後資金準備 |
| 対象者 | 18歳以上 | 18歳以上 | 原則20歳以上65歳未満の公的年金被保険者 |
| 年間投資上限 | 120万円 | 240万円 | 加入区分により異なる(年額14.4万~81.6万円) |
| 非課税期間 | 無期限 | 無期限 | 運用期間中 |
| 投資対象商品 | 金融庁指定の投資信託・ETF | 上場株式、投資信託、ETF、REITなど | 運営管理機関が提示する商品(定期預金、保険、投資信託など) |
| 税制優遇(掛金/拠出時) | なし | なし | 全額所得控除 |
| 税制優遇(運用時) | 運用益非課税 | 運用益非課税 | 運用益非課税 |
| 資金の引き出し | いつでも可能 | いつでも可能 | 原則60歳まで不可 |
NISAとiDeCoは、どちらか一方を選ぶだけでなく、両制度を併用することも可能です。
資金の流動性(引き出しやすさ)の観点からは、近い将来に使う可能性のある資金はNISA、遠い将来(老後)のための資金はiDeCoといった使い分けが考えられます。
また、現役世代で所得税・住民税を多く納めている方にとっては、iDeCoの所得控除メリットが大きい傾向があります。
自身のライフプランや資金の目的、リスク許容度に合わせて、これらの制度を賢く活用することが、効率的な資産形成の鍵となります。
投資を始めるためのステップ
投資の基本やおすすめの方法を理解したら、次は実際に投資を始めるための具体的なステップです。
口座開設から投資信託の購入方法まで、初めての方でも分かりやすく解説します。
少しずつ行動に移していくことで、投資への不安も解消されていくでしょう。
証券口座を開設
投資を始めるための第一歩は、証券口座(証券会社の口座)を開設することです。
証券口座は、株式や投資信託などの金融商品を売買するために必要な口座です。
証券会社には大きく分けて、ネット証券と対面証券の2種類があります。
インターネットを通じて取引を行うタイプの証券会社です。SBI証券、楽天証券、マネックス証券などが代表的です。手数料が比較的安く、24時間いつでも取引の注文ができる便利さが特徴です。ただし、基本的には自分で情報収集や判断をする必要があります。
店舗に行き、担当者と対面で相談しながら取引を行うタイプの証券会社です。野村證券、大和証券、SMBC日興証券などが代表的です。投資の相談ができるという安心感がある一方、手数料は比較的高めになる傾向があります。
初心者の方には、最初はネット証券がおすすめです。
その理由は、手数料が安いこと、少額から始めやすいこと、そして投資信託の品揃えが豊富なことなどが挙げられます。
特に、つみたてNISA(つみたて投資枠)の対象商品を多く取り扱っているネット証券を選ぶと良いでしょう。
口座開設の手順は、証券会社によって若干異なりますが、大まかな流れは以下の通りです。
証券会社のウェブサイトにアクセスし、口座開設の申し込みフォームに必要事項を入力します。氏名、住所、連絡先、職業などの基本情報のほか、投資経験や資産状況などについても質問される場合があります。
本人確認書類をアップロードまたは郵送します。運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなどの本人確認書類と、マイナンバー確認書類(マイナンバーカードやマイナンバー通知カードなど)が必要です。
NISA口座を開設する場合は、NISA口座開設の申し込みも行います。証券口座の開設と同時に申し込むことができます。
申し込み内容の確認と審査が行われます。問題がなければ、1週間程度で口座開設の手続きが完了します。
ログインIDとパスワードが届いたら、証券会社のウェブサイトやアプリにログインし、入金して取引を始めることができます。
初めての口座開設では、様々な書類の提出や手続きがあり、少し面倒に感じるかもしれませんが、一度開設してしまえば、その後の投資はスムーズに行えるようになります。
自分の投資スタイルや重視するポイント(手数料、取扱商品の豊富さ、使いやすさなど)に合った証券会社を選ぶことが大切です。
投資信託を選んで購入
証券口座を開設したら、次は実際に投資信託を選んで購入する段階です。
初めての方にとっては少し緊張するかもしれませんが、手順に沿って進めれば難しくありません。
まず、投資信託の選び方について、前述した選び方のポイントを踏まえつつ、より具体的に見ていきましょう。
特に投資初心者には、市場全体の動きに連動するインデックスファンドがおすすめです。「eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)」や「SBI・V・S&P500インデックス・ファンド」などが人気です。
長期投資では、わずかな信託報酬の差が大きな違いを生みます。年率0.2%以下のものを選ぶと良いでしょう。
一般的に、純資産総額が数十億円以上のファンドは安定していると考えられます。あまりに小さいファンドは、将来的に繰上償還(運用終了)のリスクがあります。
多くのネット証券では、販売手数料無料の投資信託を扱っています。購入時の余計なコスト負担を避けるためにも、ノーロードのファンドを選びましょう。
過去の実績が将来の成果を保証するものではありませんが、ベンチマーク(指数)との連動性が高いかどうかをチェックすることは参考になります。
次に、投資信託の購入方法を見ていきましょう。これもネット証券での手順を例に説明します。
ユーザーIDとパスワードを入力してログインします。
「投資信託」または「ファンド検索」などのメニューから、購入したい投資信託を探します。前述のポイントを考慮しながら、自分に合ったファンドを選びましょう。
選んだファンドの詳細ページで、基準価額の推移、信託報酬、純資産総額、ベンチマークとの連動性などを確認します。「目論見書」も必ずチェックしましょう。
「購入」ボタンなどをクリックし、購入手続きに進みます。
「一括購入」(一度に購入する方法)または「積立設定」(定期的に一定額を購入する方法)を選びます。初心者には「積立設定」がおすすめです。
一括購入の場合は購入金額を、積立設定の場合は毎月の積立金額を入力します。積立の場合は、引落日や積立開始月なども設定します。
入力内容を確認し、問題なければ注文を確定します。
注文が完了すると、購入した投資信託は証券口座内の「保有商品」などに表示されるようになります。
積立投資の設定方法は、証券会社によって若干異なりますが、基本的な流れは以下の通りです。
「積立投資」「つみたてNISA」などのメニューをクリックします。
積立設定したい投資信託を選びます。つみたてNISA(つみたて投資枠)を利用する場合は、対象商品の中から選びます。
毎月の積立金額を入力します。証券会社によっては、100円や1,000円といった少額から設定できます。
積立の引落日(毎月○日など)と、引落口座(銀行口座)を設定します。
積立を開始する年月を設定します。
入力内容を確認し、積立設定を完了します。
積立投資は一度設定すれば自動的に毎月購入されるため、わざわざ毎回購入手続きをする手間が省けます。
「つみたて投資枠」を利用する場合は、つみたてNISAでの積立設定を行うことになります。
初めての投資は不安かもしれませんが、少額から始めて徐々に慣れていくことが大切です。
最初は月々5,000円や10,000円といった無理のない金額から始め、投資に慣れてきたら少しずつ金額を増やしていくという方法もあります。
長期・積立・分散投資の原則を守りながら、着実に資産形成を進めていきましょう。
投資を成功させるためのポイント
投資を始めた後、長期的に成功させるためにはいくつかの重要なポイントがあります。
ここでは、投資を成功に導くための具体的なポイントを解説します。
長期的な視点を持つ
投資で成功するための最も重要なポイントの一つが、「長期的な視点を持つこと」です。
相場は短期的には上下に変動するものであり、一時的な下落に一喜一憂せず、長い目で見ることが大切です。
では、なぜ長期投資が重要なのか?
その理由は主に以下の点にあります。
投資期間が長くなるほど、一時的な市場の好不調が平均化され、年あたりのリターンが安定する傾向があります。例えば、日本の株式市場(TOPIX)の過去の実績を見ると、1年間の投資では大きくプラスになることもあればマイナスになることもありますが、20年以上の長期で見ると、ほとんどのケースでプラスのリターンとなっています。
長期投資の最大のメリットは、「複利効果」を最大限に活かせることです。複利とは、投資によって得られた利益(利息や分配金など)を元本に加えて再投資し、その増えた元本に対してさらに利益が生まれていく仕組みのことです。 例えば、100万円を年利5%で運用する場合、これは単利と比べて400万円以上の差です。
- 単利の場合:40年後には元本100万円+利息200万円=合計300万円
- 複利の場合:40年後には約704万円
頻繁な売買は取引手数料がかさむだけでなく、売買タイミングを誤る可能性も高まります。長期投資では、そうしたコストやリスクを減らすことができます。
そして、長期投資を成功させるためには、以下のような心構えや実践方法が役立ちます。
- 投資先の質を重視する
長期的な成長が期待できる企業や市場(インデックス)に投資することが重要です。特に初心者には、世界経済全体の成長に連動するグローバル株式インデックスファンドがおすすめです。 - 一時的な下落を恐れない
市場は短期的には上下に変動するものです。下落局面では「含み損」が発生することもありますが、それを理由に慌てて売却することは避けましょう。むしろ、長期的な視点では、下落局面は「安く買える機会」と捉えることもできます。 - 定期的な積立投資を続ける
相場の上下に関わらず、定期的に一定額を投資し続けることで、平均購入単価を抑える効果が期待できます。これが前述した「ドル・コスト平均法」の考え方です。 - 長期的な目標を設定する
「10年後に○○円」「老後のために○○円」といった具体的な長期目標を持つことで、短期的な変動に一喜一憂せずに済みます。 - 投資記録をつける
投資の目的や根拠、当時の考えなどを記録しておくと、後から振り返る際に役立ちます。また、感情的な判断を防ぐ効果もあります。
長期投資を実践する上で最も大切なのは、感情をコントロールすることです。
株価が大きく下がった時に恐怖から売却してしまったり、逆に株価が上がり続けている時に興奮して無理な買い増しをしたりといった、感情に任せた行動が投資の失敗につながりやすいのです。
長期投資では、「時間こそが最大の味方」だということを忘れないでください。
複利の力を味方につけ、短期的な変動に惑わされず、長い目で資産形成を続けていくことが、投資成功の鍵となります。
分散投資を心がける
投資を成功させるための重要なポイントの一つが「分散投資」です。
「卵は一つのカゴに盛るな」という投資格言が示す通り、投資対象を一つに集中させず、複数の異なる対象に分けて投資することで、リスクを軽減する考え方です。
分散投資が重要な理由は、一つの投資対象が値下がりしても、他の投資対象の値上がりでカバーし、資産全体の値動きを安定させる効果が期待できるためです。
それから、分散投資には主に3つの観点があります。
株式、債券、不動産(REIT)、金などの異なる資産クラスに分散投資することを指します。これらの資産は、経済環境によって値動きの特性が異なります。例えば、株式市場が下落する局面では、債券が比較的安定している場合もあります。
日本国内だけでなく、米国、欧州、アジア、新興国など、様々な国や地域に投資することを指します。各国の経済状況や政策は異なるため、ある国が景気後退に陥っても、別の国が成長している可能性があります。
投資資金を一度にまとめて投じるのではなく、購入するタイミングを複数回に分ける方法です。これにより、価格が高い時に大量に買ってしまう「高値掴み」のリスクを軽減できます。前述した「積立投資(ドル・コスト平均法)」は、この時間分散を実践する代表的な方法です。
分散投資を実践するための具体的な方法としては、以下のようなアプローチがあります。
「eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)」などの全世界の株式に投資するインデックスファンドを利用することで、一つの商品で世界中の様々な国・地域・業種に分散投資できます。
株式と債券など、複数の資産クラスに自動的に分散投資してくれるバランスファンドを利用する方法もあります。「eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)」などが代表例です。
例えば、「全世界株式」「日本株式」「先進国債券」など、異なる特性を持つファンドを組み合わせることで、より細かく資産配分を調整することも可能です。
時間の経過とともに各資産の値動きによって、当初設定した資産配分比率がずれていきます。定期的に当初の比率に戻す「リバランス」を行うことで、リスクをコントロールすることができます。
ただし、分散投資にも注意点があります。
初心者の方にとっては、まずは「全世界株式インデックスファンド」のような、それ自体が十分に分散されている商品から始めるのが最も簡単な方法です。
投資経験を積み、知識が深まれば、必要に応じて資産配分を調整していくこともできるでしょう。
分散投資は「リスクの分散」であると同時に、「機会の分散」でもあります。
どの市場や資産が将来的に最も成長するかを正確に予測することは難しいため、複数の可能性に賭けることで、リスクを抑えながらリターンを追求する賢明な投資戦略と言えるでしょう。
情報収集と学びを継続
投資で長期的に成功するためには、基本的な知識を身につけるだけでなく、継続的に情報収集と学びを続けることが大切です。
市場環境は常に変化していますし、制度の改正もあります。
最新の情報をキャッチアップし、自分の投資戦略を適宜見直していくことで、より効果的な資産形成が可能になります。
信頼できる情報源としては、以下のようなものが挙げられます。
- 公的機関のウェブサイト
金融庁、日本証券業協会、日本銀行などの公的機関は、客観的で正確な情報を提供しています。特に金融庁の「NISA特設ウェブサイト」や、金融経済教育推進機構(J-FLEC)のサイトは、初心者にもわかりやすくまとめられています。 - 大手金融機関の情報コンテンツ
大手証券会社や銀行のウェブサイトには、投資初心者向けの解説コンテンツが充実しています。もちろん自社サービスの宣伝も含まれますが、基本的な知識を得るには有用です。 - 経済・投資関連の書籍
信頼できる著者による投資初心者向けの書籍は、体系的に知識を身につけるのに役立ちます。特に長期・積立・分散投資の考え方をベースにした書籍がおすすめです。 - 投資信託の運用報告書
保有している投資信託の運用報告書は、運用状況や市場環境について客観的な情報が得られる貴重な情報源です。
また、情報収集と学びを継続するためのポイントとしては、以下のような方法があります。
毎週末や毎月など、定期的に情報をチェックする時間を設けると良いでしょう。ただし、あまりに頻繁にチェックすると、短期的な市場の変動に振り回される可能性があるので注意が必要です。
証券会社や金融機関が開催する投資セミナーや、オンライン講座などを活用すると、体系的に学ぶことができます。また、他の投資家との交流を通じて新たな視点を得ることもできます。
なぜその投資をしたのか、その時の考えや市場環境などを記録しておくと、後から振り返る際に貴重な教材となります。成功体験だけでなく、失敗経験からも多くを学ぶことができます。
PER(株価収益率)、PBR(株価純資産倍率)、利回り、ベータ値など、基本的な投資指標の意味を理解しておくと、情報を読み解く力が高まります。
学びを継続する中で大切なのは、短期的な市場予測や「儲け話」に惑わされないことです。
株式市場の短期的な動きを正確に予測することは、プロの投資家でも非常に難しいとされています。
むしろ、長期・積立・分散投資の基本原則を守り、コツコツと資産形成を続けることの方が、結果的に成功につながる可能性が高いのです。
また、自分の投資方針を明確にし、それを定期的に見直すことも重要です。
ライフステージの変化(結婚、出産、住宅購入など)に応じて、リスク許容度や投資目標が変わることもあります。そうした変化に合わせて、投資方針を適宜調整していきましょう。
投資の学びは一朝一夕で完了するものではなく、生涯続く旅のようなものです。
少しずつ知識を積み重ね、経験を積んでいくことで、より自信を持って資産形成に取り組めるようになります。
まとめ
この記事では、投資初心者がリスクを抑えながら着実に資産形成を進めていくための基本的な考え方と具体的な方法を解説してきました。
投資を成功させるためには、短期的な市場変動に一喜一憂せず、長期的な視点を持つことが重要です。
また、信頼できる情報源から継続的に学び、必要に応じて投資方針を見直していくことも大切です。
投資に「絶対に儲かる方法」はありません。
しかし、基本原則を理解し、地道に実践していくことで、長期的には資産を増やしていける可能性が高まります。
焦らず、自分のペースで、コツコツと続けていくことが、資産形成の王道と言えるでしょう。
この記事が、あなたの投資の第一歩を踏み出すきっかけとなれば幸いです。