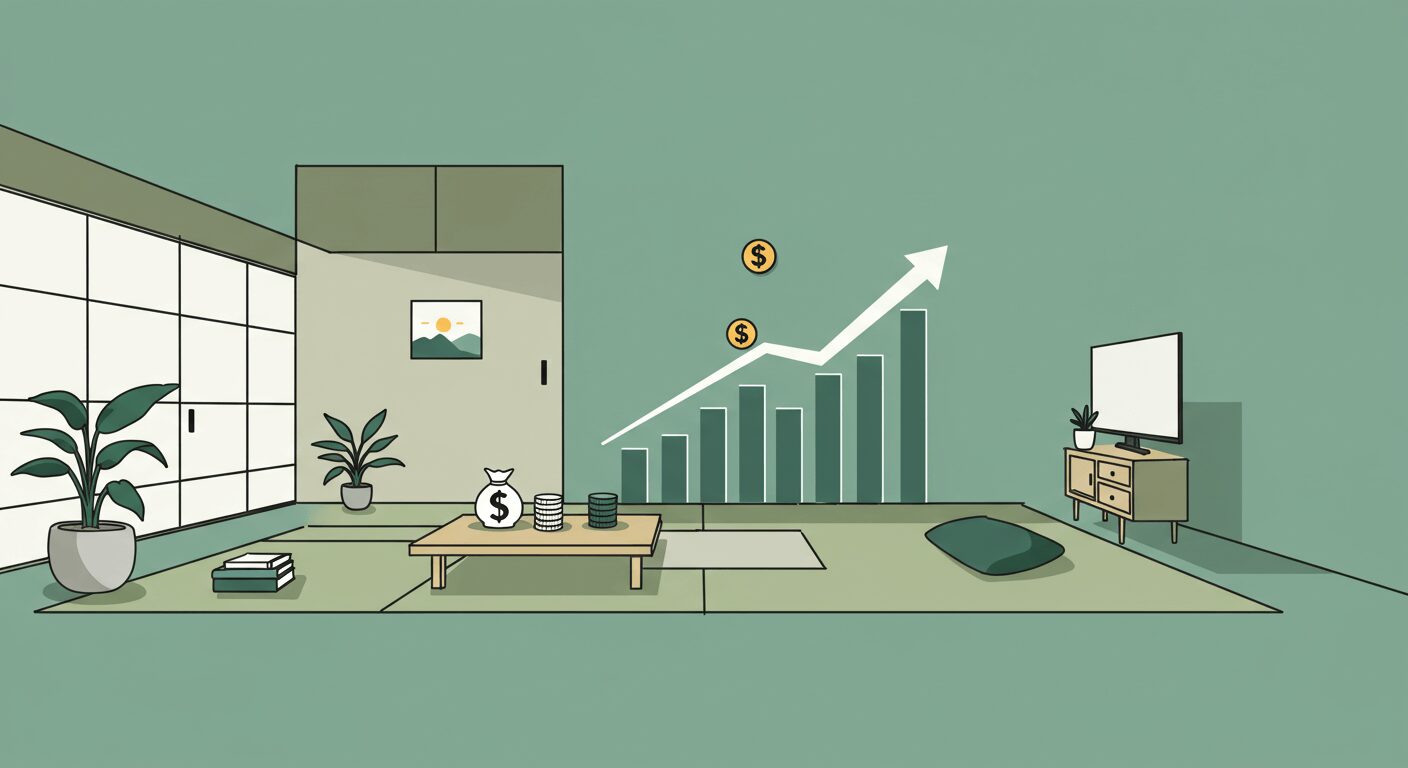【初心者向け】NISAとiDeCoの違いをわかりやすく解説!
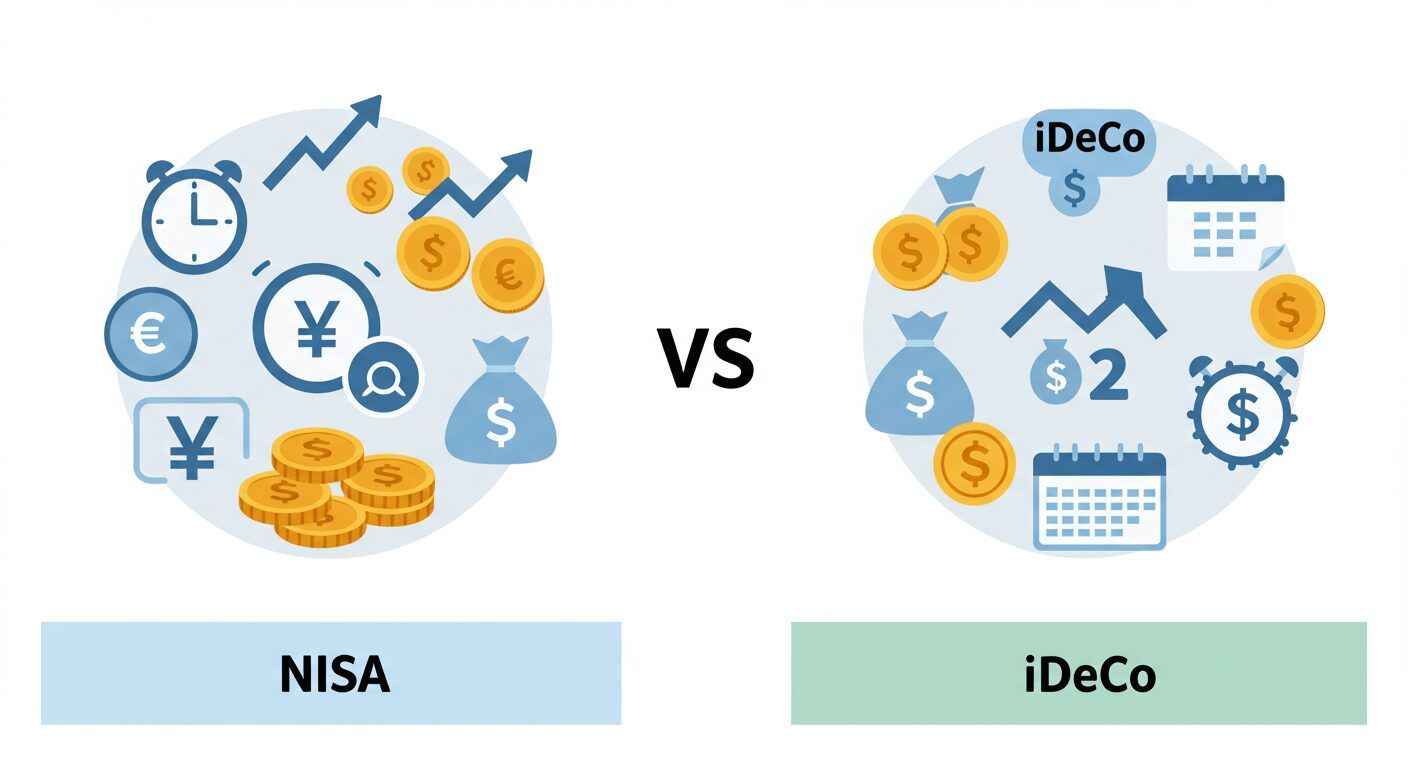
「NISA」や「iDeCo」という言葉を耳にしたことはありませんか?
将来に向けた資産形成の重要性が高まる中、今は政府主導の税制優遇制度であるNISAとiDeCoが注目を集めています。
これらの制度を利用することで、通常の投資では課税される利益が非課税になったり、所得税が控除されたりするメリットがあります。
しかし、「どちらの制度が自分に合っているのか」「何から始めればいいのか」と悩まれている方も多いのではないでしょうか。
税制や金融の専門用語が並ぶと、どうしても難しく感じてしまいますよね。
この記事では、投資初心者の方にも分かりやすく、NISAとiDeCoの基本的な仕組みから、それぞれの違い、選び方まで丁寧に解説していきます。
あなたのライフプランに合った資産形成の第一歩を踏み出すお手伝いができれば幸いです。
NISAとiDeCoはどんな制度なのか?
NISAとiDeCoは、どちらも国が推進する税制優遇制度ですが、目的や仕組みが大きく異なります。
まずはそれぞれの基本的な特徴を理解しましょう。
NISAとは?
NISA(ニーサ)は「少額投資非課税制度」(Nippon Individual Savings Account)の略称です。
この制度の最大の特徴は、投資で得た利益(運用益)が非課税になるということです。
通常、株式投資や投資信託などで得た利益には約20%の税金がかかりますが、NISA口座で行った投資については、この税金が一切かかりません。
2024年から「新NISA」として大幅に改正され、制度が恒久化されました。
現在のNISAには、次の2つの投資枠があります。
- つみたて投資枠
長期・積立・分散投資に適した投資信託に投資できる枠で、年間120万円まで投資可能です。 - 成長投資枠
上場株式、ETF、REIT、投資信託など幅広い商品に投資できる枠で、年間240万円まで投資可能です。
両枠を合わせると、年間最大360万円まで非課税で投資できます。
さらに、生涯非課税限度額として1,800万円が設定されており、この範囲内であれば期間の制限なく非課税で保有し続けることができます。
NISA口座は18歳以上の日本居住者なら誰でも開設でき、いつでも自由に資金を引き出すことができる柔軟性が特徴です。
iDeCoとは?
iDeCo(イデコ)は「個人型確定拠出年金」(individual-type Defined Contribution pension plan)の略称です。
これは、公的年金に上乗せする形で、老後の所得を確保するための私的年金制度です。
iDeCoの大きな特徴は、3段階の税制優遇があることです。
- 掛金拠出時
掛金が全額所得控除となり、所得税・住民税が軽減されます - 運用時
運用で得た利益が非課税になります - 受取時
受け取り方法によって、退職所得控除や公的年金等控除が適用されます
iDeCoは20歳以上65歳未満の公的年金加入者が利用でき、職業によって掛金の上限額が異なります。
例えば会社員(企業年金なし)なら月額23,000円、自営業者なら月額68,000円までの範囲で自由に設定できます。
ただし、iDeCoには原則として60歳になるまでお金を引き出せないという大きな制約があります。
これは、あくまで老後の資金を確保するための制度だからです。
NISAとiDeCoは何が違うのか?
NISAとiDeCoはどちらも税制優遇のある資産形成制度ですが、目的や仕組みには大きな違いがあります。
ここでは、主な違いを比較しながら解説します。
また以下の表は、NISAとiDeCoの主な違いをまとめたものです。
NISAとiDeCoの比較表(タップして表を開く)
| 比較項目 | 新NISA | iDeCo |
|---|---|---|
| 主な目的 | 一般的な資産形成、柔軟な目標設定 | 主に長期的な老後資金の準備 |
| 利用資格 | 18歳以上の国内居住者 | 原則20歳以上65歳未満(公的年金加入者) |
| 年間投資上限額 | 最大360万円(つみたて投資枠:120万円、成長投資枠:240万円) | 加入区分により変動:年額14.4万円~81.6万円 |
| 非課税保有期間 | 無期限(生涯非課税限度額1,800万円内) | 運用期間中(通常60歳以降の受取開始まで) |
| 投資対象商品 | 株式、ETF、REIT、投資信託(各枠で対象商品に制限あり) | 投資信託、保険商品、定期預金など |
| 引き出しルール | いつでも可能、柔軟。売却分の枠は翌年以降再利用可 | 原則60歳まで引き出し不可。例外は極めて限定的 |
| 税制メリット:掛金 | なし | 全額所得控除(所得税・住民税軽減) |
| 税制メリット:運用益 | 非課税 | 非課税 |
| 税制メリット:受取時 | 非課税 | 税制優遇あり(退職所得控除・公的年金等控除) |
| 手数料概要 | 口座管理料・売買手数料は無料の場合が多い。商品固有の費用あり | 加入時手数料、毎月の口座管理手数料、商品固有の費用、給付時手数料など |
目的の違い
NISAとiDeCoの最も基本的な違いは、その目的にあります。
NISAは幅広い資産形成を目的とした制度です。老後資金はもちろん、住宅購入、教育資金、旅行資金など、様々な目的のための資産形成に活用できます。つまり、特定の目的を限定せず、自由度の高い資産形成が可能です。
iDeCoは明確に老後の所得確保を目的とした年金制度です。そのため、60歳になるまで原則として資金を引き出せないという制約がありますが、その代わりに強力な税制優遇が与えられています。
例えば、35歳のAさんが「10年後に住宅購入の頭金として使いたい」と考えているなら、NISAが適しています。
一方、「老後の資金を確実に準備したい」というBさんには、iDeCoがより適しているでしょう。
非課税期間の違い
NISAは2024年からの新制度で、非課税保有期間が無期限になりました(ただし、生涯非課税限度額1,800万円の範囲内)。一度投資したらいつまでも非課税で保有でき、売却して再投資する場合も、翌年以降に非課税枠が復活するので柔軟に運用できます。
iDeCoは原則として60歳になるまで非課税で運用し、60歳以降に給付を受け取る仕組みです。受け取り時にも税制優遇がありますが、基本的には長期間(数十年)にわたって資金を固定することを前提としています。
すぐに資金が必要になる可能性がある場合は、NISAの方が柔軟に対応できるでしょう。
投資対象の違い
NISAでは、特に「成長投資枠」で個別株式やETF、REITなど幅広い商品に投資できます。
自分の投資スタイルや関心に合わせて、様々な商品を選択できる自由度があります。「つみたて投資枠」でも長期・積立・分散投資に適した投資信託に投資できます。
一方、iDeCoでは、選択した金融機関が提供する投資信託、保険商品、定期預金などから選ぶことになります。
金融機関によって選択できる商品が限定されており、一般的には投資信託が中心となります。株式の個別銘柄を選んで投資することはできません。
引き出しやすさの違い
NISAの大きな特徴は、いつでも自由に資金を引き出せる点です。
急な出費が必要になった場合でも、ペナルティなく資金を引き出すことができます。売却した分の非課税枠は翌年以降に復活するため、一時的に資金が必要な場合も安心です。
一方、iDeCoは原則として60歳になるまで資金を引き出すことができません。
例外は、死亡した場合や高度障害状態になった場合、あるいは極めて限定的な条件を満たす「脱退一時金」の場合のみです。
この厳格な引き出し制限は、老後資金を確実に確保するためのものですが、途中で資金が必要になった場合には対応できない点が大きなデメリットとなり得ます。
「将来の資金ニーズが不確実」「いざという時のために柔軟性を確保したい」という方にはNISAの方が適しているでしょう。
節税効果の違い
NISAの税制優遇は、運用で得た利益(譲渡益・配当金・分配金)が非課税になる点です。
通常約20%の税金がかかるところが、全くかからないというメリットがあります。
ただし、投資元本(掛金)に対する税制優遇はありません。
先ほども説明しましたが、改めてiDeCoの税制優遇は3段階あります。
- 掛金拠出時
掛金全額が所得控除され、所得税・住民税が軽減 - 運用時
運用益が非課税 - 受取時
退職所得控除や公的年金等控除が適用され、税負担が軽減
特に所得税率が高い方(=所得が多い方)ほど、iDeCoの所得控除による節税効果は大きくなります。
例えば、所得税率33%の方が年間24万円をiDeCoに拠出すると、約10万円の税金が軽減されます。
NISAとiDeCoってどっちを選べばいいの?
NISAとiDeCoは、それぞれ特性が異なるため、あなたの状況や目的に合わせて選択することが重要です。
以下では、目的別、ライフステージ別の選び方と、両方を併用する方法について解説します。
選び方①:目的別
投資の目的によって、NISAとiDeCoのどちらが適しているかが変わってきます。
老後資金を着実に準備したい場合は、iDeCoを優先的に活用することをおすすめします。
iDeCoは老後の所得確保を目的とした年金制度であり、掛金の所得控除による節税効果と、60歳まで引き出せないという制約によって、強制的に長期間積み立てることができます。
特に所得が多く、税率の高い方にとっては、iDeCoの所得控除による節税効果は非常に大きなメリットとなります。
住宅購入のための頭金など、60歳前に使う予定の資金を準備する場合はNISAが適しています。
NISAは、いつでも必要なタイミングで資金を引き出せる柔軟性があるため、住宅購入などの中期的な目標に向けた資金形成に向いています。
ただし、住宅購入のような重要な資金を、価格変動リスクのある投資商品のみで準備することには注意が必要です。
市場の状況によっては、必要な時期に資産価値が目減りしている可能性もあるため、預貯金など安全性の高い資産と組み合わせることも検討すべきでしょう。
子どもの教育資金も、通常は60歳前に必要となるため、NISAが適した選択肢となります。
特に、子どもが小さいうちから長期間かけて準備する場合は、つみたて投資枠を活用した積立投資が効果的です。
教育資金も住宅購入資金と同様に、必要な時期が決まっているため、iDeCoは適していません。
また、教育資金の一部は、安全性の高い預貯金などで確保しておくことも検討すべきでしょう。
選び方②:ライフステージ別
年齢やライフステージによっても、NISAとiDeCoの活用方法は変わってきます。
20代は投資期間を最も長く確保できる時期です。
この時期に投資を始めることで、複利効果を最大限に活かすことができます。
- まずはNISAのつみたて投資枠から始めることです。少額からでも長期・積立・分散投資を実践でき、将来的にいつでも引き出せる柔軟性があります。
- 所得が安定してきたら、iDeCoも併用して始めましょう。早くから始めるほど、60歳までの運用期間が長くなり、複利効果が大きくなります。
例えば、25歳から月5,000円をつみたてNISA、月5,000円をiDeCoで運用を始めた場合、60歳までの35年間で、年率5%の運用ができれば、それぞれ約460万円、合計約920万円になる可能性があります。さらにiDeCoの場合は、掛金の所得控除による節税効果も得られます。
30代は収入が増加する一方で、結婚、出産、住宅購入など大きな支出が重なる時期でもあります。
柔軟性と税制優遇のバランスが重要です。
- 住宅購入などの予定がある場合は、NISAを優先的に活用しましょう。必要な時に資金を引き出せる柔軟性が重要です。
- 長期的な老後資金として確保する分は、iDeCoを活用するのが効果的です。特に所得が増えてきた30代は、iDeCoの所得控除による節税効果も大きくなります。
例えば、35歳の方が住宅購入を5年後に控えている場合、まずはNISAで頭金を準備しつつ、老後資金としてiDeCoに毎月1万円程度拠出するといった使い分けが考えられます。
40代になると、老後の生活設計がより具体的になり、資産形成のペースを上げる時期です。
所得も安定していることが多いため、税制優遇を最大限に活用することが重要です。
- iDeCoの掛金を上限まで拠出し、税制メリットを最大限に活用しましょう。
- iDeCoの枠を超えた投資や、より柔軟な資金管理が必要な部分はNISAを活用します。
例えば、45歳の会社員Dさん(企業年金なし)なら、iDeCoで月額上限の23,000円(年間276,000円)を拠出し、残りの投資資金をNISAで運用するといった方法が考えられます。
50代は退職が視野に入り、資産の保全と成長のバランスがより重要になります。
リスク管理に注意しつつ、最終的な資産形成を進める時期です。
- iDeCoへの拠出は継続できますが(原則65歳未満まで)、運用期間は短くなるため、運用商品の選択にはより慎重になりましょう。
- NISAは退職前後の資金管理や、iDeCoの受取開始までのつなぎ資金など、柔軟な活用が可能です。
例えば、55歳の方があと5年で退職予定の場合、iDeCoはやや控えめにして、NISAでより安全性の高い商品を選ぶなど、リスクを抑えた運用を心がけるとよいでしょう。
選び方③:NISAとiDeCoの併用
NISAとiDeCoは併用可能であり、組み合わせることでより効果的な資産形成が可能になります。
iDeCo優先の場合は、まずiDeCoの掛金を上限まで拠出し、所得控除メリットを最大限確保します。
その上で、余裕資金があればNISAを活用するアプローチです。
老後資金準備と節税効果を最優先する、特に所得の高い層に適した戦略です。
「60歳前に使う可能性のある資金(住宅、教育など)の準備を優先する場合」や、「iDeCoの所得控除メリットが小さい(所得が低いなど)場合」に、NISAを優先的に、あるいはiDeCoと並行して、家計に無理のない範囲で両方に拠出するアプローチです。
iDeCoの所得控除によって還付された、あるいは軽減された税金分を、そのままNISAでの投資に回すという具体的な手法も効果的です。
これにより、税制優遇をさらなる投資へと繋げることができます。
NISAとiDeCoを始めるには?
NISAとiDeCoを始めるには、まず口座開設が必要です。
ここでは、口座開設の方法や金融機関選びのポイントについて解説します。
口座開設の方法
NISA口座は、証券会社や銀行などの金融機関で開設できます。
開設手続きは以下のようになります。
証券会社(ネット証券、対面証券)や銀行から選びます。
選んだ金融機関のウェブサイトや窓口で申込み手続きを行います。
口座開設には、マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カードと本人確認書類が必要です。
金融機関を通じて税務署に申請します(金融機関が代行してくれます)。
審査が通れば口座開設完了の通知が来ます。
NISA口座は1人1口座のみ開設可能で、年単位で金融機関を変更することもできます。
iDeCo口座の開設はNISAに比べてやや複雑で、以下のような流れになります、
証券会社、銀行、保険会社などから選びます。
選んだ金融機関から加入申込書を入手し、必要事項を記入します。
マイナンバーの分かる書類、本人確認書類、勤務先の証明書(会社員の場合)などが必要です。
記入した申込書と必要書類を、選んだ金融機関に提出します。
申込書は金融機関から国民年金基金連合会に送られ、審査されます。
日本年金機構で加入者資格の確認が行われます。
審査が通れば、iDeCo加入者証が送られてきます。
iDeCoの開設手続きは、申込みから完了までに1〜2か月程度かかることがあります。
金融機関選びのポイント
NISA口座を開設する金融機関を選ぶ際のポイントは以下の通りです。
- 取扱商品の充実度
特に成長投資枠を活用したい場合、取り扱っている株式、ETF、投資信託などの品揃えが豊富かどうかを確認しましょう。 - 手数料
口座管理料や売買手数料が無料か、投資信託の信託報酬などのコストはどうかを比較しましょう。 - 使いやすさ
ウェブサイトやアプリの使いやすさ、情報提供の充実度などを確認しましょう。 - サポート体制
投資初心者の場合、問い合わせ窓口や情報提供が充実しているかどうかも重要です。
一般的に、SBI証券や楽天証券などの大手ネット証券は、手数料の低さや取扱商品の豊富さから人気があります。
対面証券や銀行は、直接相談できる安心感がありますが、コストが高くなる傾向があります。
iDeCoの金融機関(運営管理機関)を選ぶ際のポイントは以下の通りです。
- 手数料
特に運営管理機関手数料が大きく影響します。金融機関によって月額0円から数百円まで差があります。 - 商品ラインナップ
提供されている投資信託の種類や特徴、信託報酬の水準などを確認しましょう。 - 情報提供・サポート
投資初心者の場合、情報提供やサポートが充実しているかも重要です。
iDeCoは長期間(数十年)にわたって付き合う制度なので、特に手数料が低く、商品ラインナップが充実した金融機関を選ぶことが重要です。
SBI証券、楽天証券、マネックス証券などのネット証券は、低コストで人気があります。
よくある質問
NISAとiDeCoについて、初心者の方がよく抱く疑問にお答えします。
- Q1:NISAとiDeCoは両方利用できますか?
-
A: はい、NISAとiDeCoは併用可能です。それぞれの制度には投資上限額がありますが、両方の制度を最大限活用することで、より効果的な資産形成が期待できます。ライフプランや目的に応じて、両制度をバランスよく利用するのがおすすめです。
- Q2:手数料はどのくらいかかりますか?
-
NISAは口座管理料や売買手数料が無料の金融機関が多いですが、投資信託には信託報酬がかかります。一般的に年率0.1%~1.5%程度で、つみたて投資枠の対象商品は比較的低コストです。一方、iDeCoは複数の手数料がかかります。
- 加入時手数料:約2,829円(一回のみ)
- 毎月の口座管理手数料:国民年金基金連合会へ105円、事務委託先金融機関へ約66円、運営管理機関(選んだ金融機関)への手数料(0円~数百円と差が大きい)
- 投資信託の信託報酬
- 受取時の手数料:振込ごとに約440円
特にiDeCoは金融機関によって手数料が大きく異なるため、比較検討が重要です。
- Q3:途中で解約してお金を引き出せますか?
-
NISAはいつでも自由に売却・引き出しが可能です。売却した分の非課税枠は翌年以降に再利用できます。一方、iDeCoは原則60歳まで引き出せません。例外は以下の極めて限定的なケースのみです。
- 死亡時(遺族が受け取り)
- 高度障害状態になった場合
- 特定の条件を満たす「脱退一時金」の場合(加入期間が短く、資産額が少ない場合など)
この引き出し制限は、iDeCoを選ぶ際の最も重要な考慮点の一つです。
- Q4: 投資初心者におすすめの運用方法は?
-
投資初心者には「長期・積立・分散」の基本原則に沿った運用がおすすめです。NISAのつみたて投資枠やiDeCoを利用して、以下のような運用を検討しましょう。
- 少額から始める
NISAは月100円から、iDeCoは月5,000円から積立可能です。 - インデックスファンドを活用
全世界株式や先進国株式など、幅広く分散されたインデックスファンドを中心に選びましょう。 - 定期的に積立
毎月一定額を積み立てるドルコスト平均法で、価格変動リスクを抑えられます。 - 長期保有
短期的な値動きに一喜一憂せず、長期的な視点で運用しましょう。
具体的には、「eMAXIS Slim 全世界株式」「ニッセイ外国株式インデックス」などの低コストの全世界・先進国株式インデックスファンドは、初心者にもおすすめの商品です。
- 少額から始める
- Q5: NISAのつみたて投資枠と成長投資枠は、別々の金融機関で利用できますか?
-
いいえ、できません。NISA口座は1人1口座、1金融機関のみで開設可能であり、つみたて投資枠と成長投資枠はその1つの口座内で利用します。つまり、両方の枠を別々の金融機関で分けて使うことはできません。
- Q6: NISAで利益が出たら確定申告が必要ですか?
-
いいえ、NISA口座での利益は非課税のため、確定申告の必要はありません。これがNISAの大きなメリットの一つです。配当金を非課税で受け取るためには、株式数比例配分方式を選択する必要がある点には注意しましょう。
- Q7: iDeCoの掛金は、どうすれば所得控除を受けられますか?
-
会社員の方は、主に年末調整で所得控除を受けられます。金融機関から送られてくる「小規模企業共済等掛金払込証明書」を勤務先に提出します。
自営業者等の方は、確定申告の際に申告書に掛金額を記入し、証明書を添付して控除を受けます。所得控除を受けるためには、適切な手続きを確実に行うことが重要です。
- Q8: 海外に引っ越す場合、NISAやiDeCoはどうなりますか?
-
NISAは原則として非居住者になると口座閉鎖が必要です。ただし、5年未満の海外転勤など一定の要件を満たせば、手続きを行うことで継続保有が可能な場合があります(新規買付はできません)。
iDeCoは非居住者になると掛金の拠出資格を失いますが(国民年金に任意加入する場合などを除く)、既存資産の運用は60歳まで継続されます。
海外移住を計画している場合は、事前に金融機関に確認することをおすすめします。
- Q9: 投資でリスクを取りたくない場合、どうすれば良いですか?
-
投資にはリターンに応じたリスクが伴いますが、リスクを抑えた運用方法もあります。
- iDeCoでは、元本確保型の商品(定期預金や保険商品)も選択できます。ただし、低リスクは低リターンにもつながります。
- NISAでは、バランスファンドや債券比率の高い商品を選ぶことで、リスクを抑えられます。
- 長期・分散・積立という原則を守ることで、市場変動のリスクを軽減できます。
投資初心者の方は、徐々にリスクに慣れていくことも大切です。まずは少額から始め、投資について学びながら経験を積んでいきましょう。
- Q10: NISAとiDeCoは将来どうなるのでしょうか?制度が変わる可能性はありますか?
-
制度は将来変更される可能性があります。新NISAは2024年から恒久化されましたが、細かい制度内容は変更される可能性があります。iDeCoも、年金制度全体の見直しに伴って変更される可能性があります。
ただし、急に不利な方向に大きく変わることは少なく、既存の利用者への経過措置が設けられるケースが多いです。最新の情報をチェックしつつ、現在利用できる制度を活用することが大切です。
まとめ
NISAとiDeCoは、どちらも資産形成に役立つ税制優遇制度ですが、特徴や向いている目的が大きく異なります。
重要なのは、今回の記事で紹介した制度について理解し、自身のライフプランやニーズに合わせて選択することです。
そして、早く始めるほど複利効果は大きくなるため、少額からでもまずは一歩を踏み出すことをおすすめします。
将来の経済的な安心のために、NISAとiDeCoという強力なツールを賢く活用していきましょう。
必要であれば、ファイナンシャルプランナーなどの専門家に相談することも有効な選択肢です。